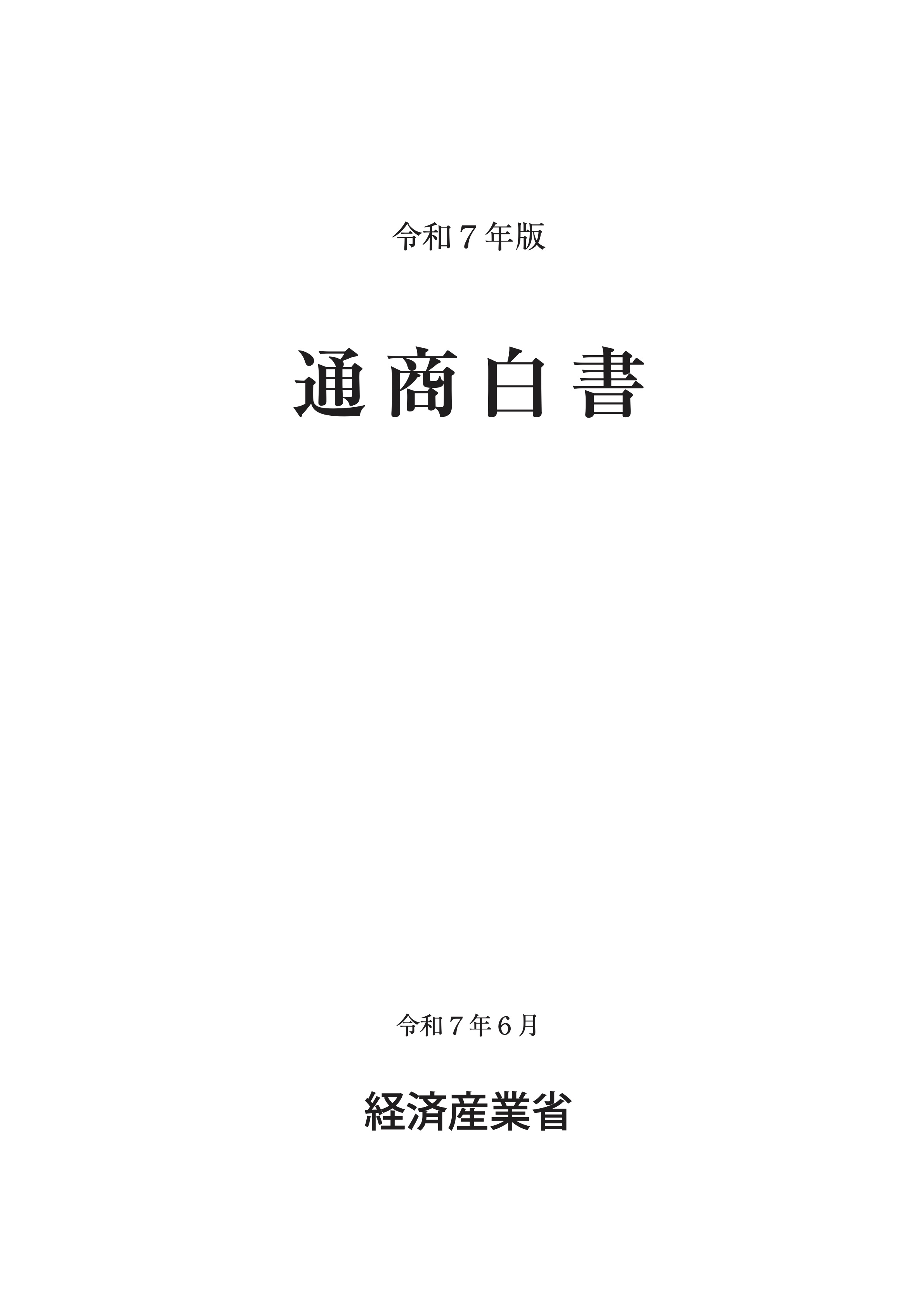2025年8月11日付日経に『相互関税「不均衡是正なら氷解」 ベッセント米財務長官インタビュー』という記事があった。私が注目したのは以下の記述(下線は筆者)である。
ベッセント氏は関税政策の目的について「国際収支のバランスを取り戻すことにある」と答えた。米国は経常赤字が1兆1853億ドル(約175兆円、2024年)と主要国で突出しており、同氏は将来的な金融危機につながるリスクを指摘している。
ベッセント財務長官は金融出身で自らLGBTQを表明している共和党員。トランプ氏支持を表明しているのでちょっと剣呑なイメージを抱いていたが、どうやらかなり長期的な視点をもっている人のように感じるようになった。ファンドの運営もしていたから、リスク分析については相当の能力を有しているのは間違いなく、関税のリスクについては百も承知の上で任務を遂行している。「トランプ大統領の任期中かはともかく、時間が経過すれば日米の国際収支はバランスを取り戻せる」とも述べており、関税の負の影響を許容しても、長期的な米国の繁栄のためには、大きな変化が必要だと考えているのだろう。
赤澤大臣は官僚出身で官僚出身のMBAホルダーで、恐らくベッセント氏との間では合理的な話が話ができると考えていると思われる。ベッセント氏からも好感を持たれているように思われる。
政治のことはよくわからないが、私は赤澤氏が日本を代表して交渉に当たる際に基盤として通商白書2025作成時に検討された情報を用いているのではないかと思う。
通商白書2025は400ページを超える厚みのある資料だが、拾い読みをするだけでも経産官僚の気合が感じられる。トランプ政権の誕生はどう考えても国難で、どう対応すべきか適切な判断材料を提供するのは官僚の使命だ。2024年版も流し読みしたが、迫力がぜんぜん違うと感じた。内外の様々なデータを分析し、対米や対中という視点ではなく、世界で何が起きているかについて第一部「国際経済秩序の転換期に増幅する不確実性」で記載している。数値化にも挑戦していて、4-1の地政学的な距離も興味深い。第一部を読むと、いわゆる一つ一つのディールではなく、もっと大局的な国際経済の現状と転機について記載している。日本からの視点でのバイアスが入らないように注意が払われている。
第二部「包摂性、規模の経済と非対称依存、サービス付加価値」で課題抽出がなされていて、米国の変容、中国のリスク、日本の現状について書かれている。これもなかなか読み応えがあり、日本が強国になるため、あるいは権益を維持するためという視点はかなり押さえられている。むしろ、共存共栄を目指すためにどんな選択肢があるのかが浮かび上がるように書かれていると感じた。
第三部「戦略・施策」は、私にとっては面白いものではなかった。本来、政治家が考えるべきことなのだろう。もちろん、書かれていることはもっともなのだが、面白くはない。制定すべき制度案は複数あって良いし、それから何を選択するかは、民度による。そこまで官僚が書くのは、成長期を過ぎた国では適切だとは思えなかった。それでも、それを最大公約数として読んだ上で、民間企業も将来を考えたら良いだろうと思った。
3-1-1で「二国間及び多国間において対話を粘り強く進め、公正な貿易政策を推進しつつ、経済安全保障を確保し、各国とのウィンウィンの関係構築を目指すことが重要である」と書かれている。もちろん、大前提として「通商政策の一義的な目標は、我が国企業の海外展開支援や我が国企業が活躍する環境・ルール整備、その基盤としての諸外国との経済関係の強化等を通じ、「世界の課題解決を通じて我が国の世界における付加価値を最大化すること」である。」があるわけだが、その前提をおいても「ウィンウィンの関係構築」の重要性を挙げているに好感する。今回の関税交渉でも、赤澤大臣は、相手(トランプ)の希望を聞いた上で、双方にとって利になる解を探すというという姿勢が際立っていた。さらに、日本は2国間のディールだけで考えているわけではなく、暴君の主張を聞きながら、「二国間及び多国間において対話を粘り強く進め、公正な貿易政策を推進しつつ、経済安全保障を確保し、各国とのウィンウィンの関係構築を目指」したと感じる。私は、その姿勢をとても好感している。
グローバルサウスに関する言及は割とボリュームがあって、内容に異論はない。官僚的にはこれで良いのだろうが、「中堅・中小企業の輸出・海外展開支援」あたりを見ると、上から目線が鼻につく。国内の人材育成は文科省管轄だろうから、その議論を避けているように見える。3-2「2024 年度の取組」は、ちょっと言い訳感があるので、付録に移して、もう少し長くしても良いのではないかと思った。
3-1と並行して、民間企業、特にイノベーションを担うであろう将来人材に向けてのメッセージが欲しいと思った。エストニアで活動していると、人口100万人強の国では、起業家は国内マーケットの小ささを知っていて、最初からグローバル(といってもEUレベルというイメージはある)を目指している。だから、政府補助金よりはマーケットを見ているように思う。戦後の日本も貧乏だったから、米国、世界にマーケットを求めて進出していった。少なくない若者は、それが格好良いことだと思ったのだ。留学奨学金は魅力的だったが、奨学金があるから留学した訳では無い。
個々のイノベータが関心を持つ部分は狭い。第一部、第二部には百科事典的に相当な情報が含まれているが「世界の課題解決を通じて我が国の世界における付加価値を最大化すること」が官僚の目標だとしても、世界の課題を見えやすくして、ここ掘れワンワン的な煽りも必要だろう。特にグローバルサウスに自力のあるベンチャーが投資して、そこでの課題解決に貢献しつつ、グローバルマーケットで存在感をもつ企業に化けていくような変化が必要なのではないかと思う。
今年の通称白書は一読の価値があると思う。