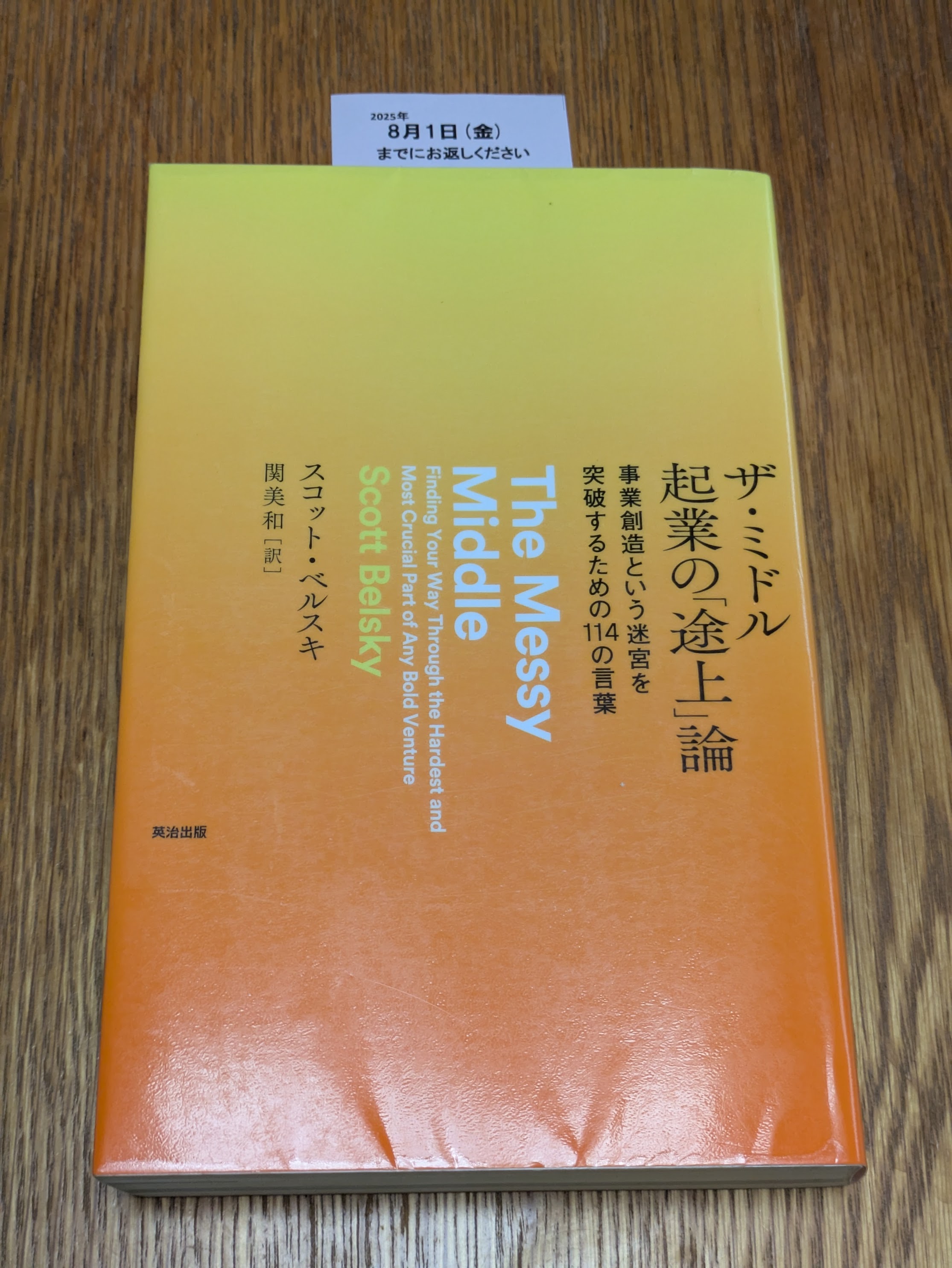ザ・ミドル 起業の「途上」論読了。550pの本で厚みがあるが、実際に読んでみると1,000p以上の読み応えがある。本当に読んで良かった。
もともとは、佐谷さんのスコット・ベルスキ『ザ・ミドル 起業の「途上」論』に刺激されて読み始めたものだ。彼が引用として書いた「この世で一番中毒になりやすいのはヘロインと月給」(P48、著者ではなくベンチャーキャピタリストの発言の引用)に激しく共感したのだ。ヘロインは知識として知っているだけだが、月給は私の人生の長い期間、私を縛っていた(中毒させていた)ものであり、今なら、国家が支払う月給(年金)に中毒(依存)している。それがだめだとは言わないが、その危険性は自らの道を選び取る力を削ぐところにある。昨日と同じことを繰り返しているだけで生きていけるのはありがたいことだが、長期で見れば必ず環境は変わっていくから、やがてその怠惰の報いを受けることになる。「この世で一番中毒になりやすいのはヘロインと月給」という話は、Part1「耐える」の1章の「苦痛と未知の中でチームを導く」の最初の「報酬系を騙す」で出てくる。その節の最後の部分では、「チームの文化を育てるにあたって「成功」の基準を下げることを僕はお勧めする」と書いてあって、ヒントが書かれている。今まで接点をもったスタートアップで良いチームだと感じたところには文化があった。短期で良い業績を出すかどうかと文化が確立されているかは必ずしも相関しないし、時期によってチームも文化も変化する。
Part1の1章の「苦痛と未知の中でチームを導く」の最後の節「やるべきことをやる」の最後は、やはり引用だが、「最も困難で大変な時期に、ただ歩みを止めずに努力を続け、勇気を出してやるべきことをやり続ければ、限りない可能性が生まれる。」という言葉がある。「あきらめたらそこで試合終了ですよ」と同じだ。経営陣にいる人達も一人ひとりの意見が一致することはない。やり続けることを断念する自由もあるし、新たな道を選択する自由もある。トップの交代が会社を強くすることもあるし、そうでない時もある。「やるべきことをやる」は孤独との戦いでもある。
次の2章は「決意を強める」で最初の節は「自己認識こそが、ただひとつの「持続可能な競争優位性」」だ、息をつかせずに読み進めさせられる。5つのポイントがまとめられている。その一つに「自己認識とは、自分の感情を深く理解し、何が自分の気に障るのかがわかるようになることだ。」とある。誰にでも気に障ることはあり、その傾向は人によって違う。相手の気に障ることには触れないのが上手な世渡りの鉄則となる(逆手に取る道もある)。逆に自分が気に障るのがどういう場合なのかがわかっていれば冷静さを保ちやすい。この書籍は生きるヒントのてんこ盛りだ。2章の最後の節は「前進するにはリセットしかない」で結びは「あなたは立ち直れるし、成功できる。一歩一歩、進んでいくしかない。」だ。素晴らしいチームにも、必ず挫折は訪れる。
Part1最後の3章は「長丁場を闘う」だ。この終わりがP142で全体の約3割となる。「結びはやらなくてもいい仕事を進んでやっていれば、自分の守備範囲しか守らない人よりも大きな影響力を持てるようになるはずだ。」とある。将来の経営者の心構えについてもきちんと書かれている。
Part2は「波に乗る」は3つのサブパート「チームを最適化する」1〜4章、「プロダクトを最適化する」5〜6章、「自分を最適化する」7〜10章からなる。350ページあって、サブパートがそれぞれ一冊の本として存在して良いと思われるほど充実している。分冊すれば、恐らく分量は1.5倍から2倍になってより深くなりそうに感じられる。実際「プロダクトを最適化する」の冒頭部には「この章(サブパートのこと)は、ここだけを独立した本としても読めるように書いた。」とある。
「チームを最適化する」でも印象に残る記述はたくさんあるが、一つ選ぶのであれば1章の「極端な人を避けていると大胆な結果が生まれない」で「自分が苦手な人と付き合うと、欠点ばかりが見えてしまう。なぜ自分がそう感じるのかを考えず、相手が悪いと決めつけてしまうのは、観点で臆病な生き方だ。」という主張だ。リーダーは多忙で、日々決断を下していかなければいけないが、その決断に自己認識不足によるバイアスが入ってしまえば、チーム、チームメンバーの潜在力を引き出すことはできない。日本語だと胆力とでも言えばよいのかもしれないが、正論だと思う。あと、4章「解決への障害を取り除く」の「時間をかけて「調理」する」も興味深い。そこには著者自身の感想として「この本は、何年もかけて弱火でじっくり煮込んだシチューのようなものだ。」という記述がある。スピードだけに焦点をあててもうまくいくわけではない。経営者に対する警句でもある。
「プロダクトを最適化する」はプロダクト開発に関わる人なら、必ず学びが得られるだろう。過去の自分の失敗が思い起こされることもあって、コメントは控える。
「自分を最適化する」は7章「計画と意思決定」、「計画は必要だがそれにこだわってはいけない」という節から始まる。経営トップが合理的な判断ができるためのノウハウが散りばめられている。経営者には色々なタイプがあるが、分野の専門家のみが成功するわけではない。8章「ビジネスの勘を鍛える」は「直感に反するアドバイスを掘り起こし、自分の勘を鍛える」という節から始まる。このサブパートは、投資家の視点で書かれているように見える。社員から見たときの理想的な経営トップ、あるいはこの上司の下で働きたい選挙の勝利者は、必ずしも経営トップとして成果が出せるわけではない。顧客や投資家などの外からの視点で見ると、別の視点が得られる。経営トップが遊んでいるように見えても、その遊びで「ビジネスの勘を鍛える」ことに資しているかもしれない。経営層だけではなく、一般社員もこの部分に目を通しておいて損はないと思う。
Part3は「ゴール直前」で「ゴールテープを切る」、「バトンを渡す」、「終わりなき旅」の3章からなる。主に著者の感想が述べられていて、ほとんどの読者にとってはすごく役に立つことが書いてあるというインパクトはないだろうが、Part2まで読み込んだ後で最後に読むと味わいがある。佐谷さんが引用していた2章の節「自分のやり方で終わる」では達観を感じられる。成功を目指して歩み始めて、一定の成功を得られた時、歩み始めたときの自分とは違う自分に変化している。改めて自分に「おまえは、やるべきことをやっているか?」と問わずにはおられなくなった。
ちなみに佐谷さんとは、前職を退任、創業直後に彼が経営する株式会社旅と平和の経堂のコワーキングスペースで出会った。当初は自由人という印象が強かったが、今は凄腕の経営者として尊敬している。引用したNoteで株式会社ドキュメンタリー4の設立者の一人であることを知った。つい、起業からスケールする華やかなベンチャーを想像してしまうが、「「旅と平和」 創業の目的」に書かれているようなベンチャーも素晴らしいと思う。私は幸せを増やすような仕事を持続的に経営できる人に憧れる。