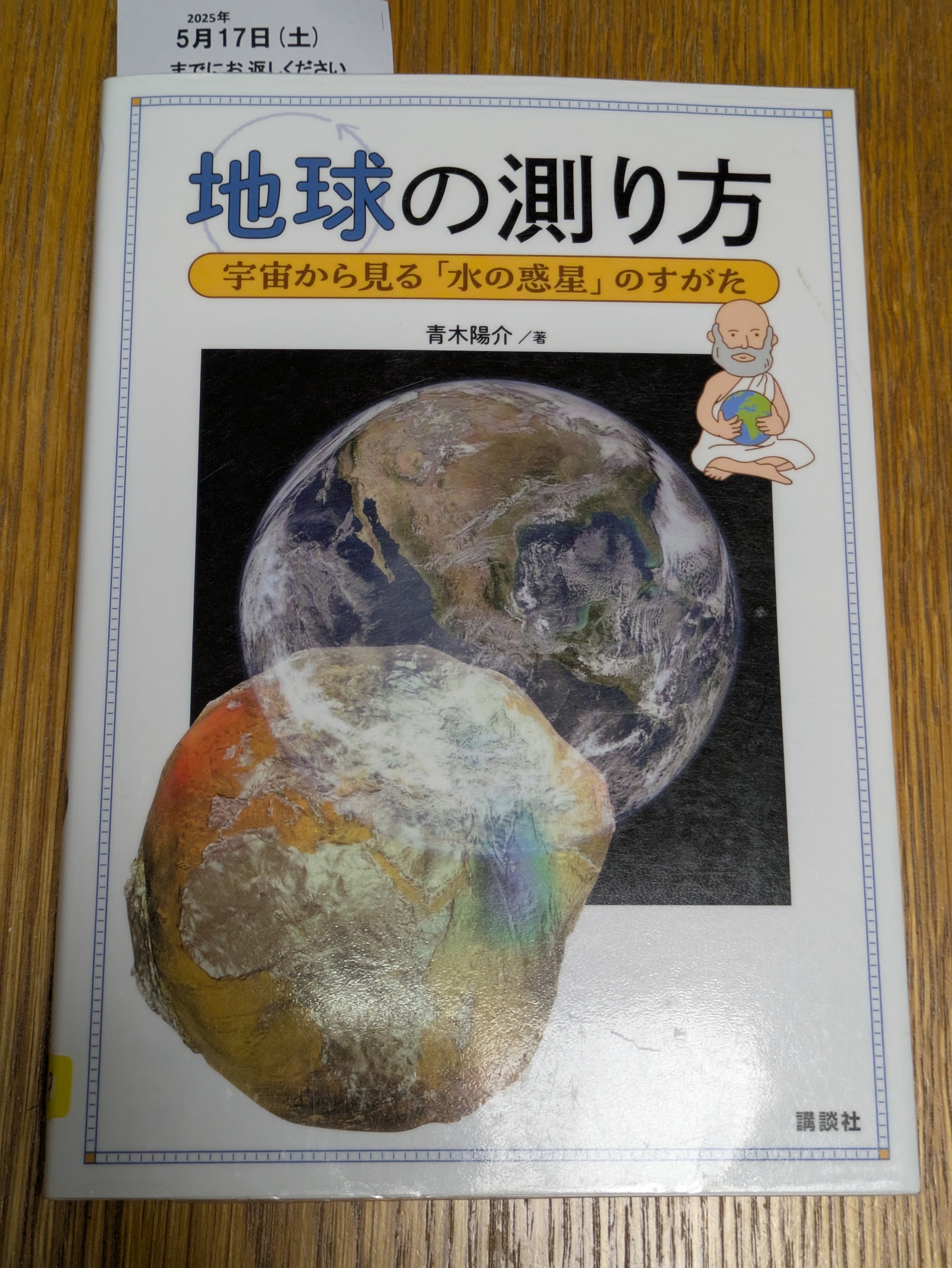地球の測り方読了。
東大地震研の准教授が書いた測地学の本なので、地図から考える人とは視点が違い、私が知りたいと思っていたことが多数含まれていて感動した。著者の博識さはもちろん、未解決問題も提示しているので、現役研究者あるいは地理空間情報エンジニアには素晴らしい導入ガイドになっているように感じた。
もとは、羽田氏のTweetを見て図書館に申し込んだのだと思う。札幌出張の合間のことだと思うのだが、記憶が曖昧だ。
昨日のイベント帰りに紀伊國屋で雑誌『Interface』を買ったついでに物色してたら、面白そうな本を発見。
青木陽介(2025)『地球の測り方 宇宙から見る「水の惑星」のすがた』講談社https://t.co/0go1YYGmVg
最近測地系を調べる機会が多いので手にしました。一般書なので火山や地震などの応用が多め。 pic.twitter.com/JdFGPNxpGk— 羽田 康祐 / 地図とGISの人 (@kohsuke_hada) April 13, 2025
8章の『1日の長さは一定なのか』までは、ほとんど教科書のような内容でわかりやすい。潮汐力のあたりの話から、かなりアドバンスコースに入っている(と思う)。
一回読み終わってから、もう一度1章『地球を知るホットな学問 測地学とは何だろうか』を読み直すと1.3で地球の内部構造を知りたいと書かれている。1.2でも形の変化を知りたいと書かれていて、地面は動かないという原則ではなく、変化するものだという前提で書かれている。GNSSの発展、衛星やセンサーの進化でどのようにわかるようになってきたかが理解できる。同時に、日本が選考していた部分で、新技術の台頭で追い越されてしまう部分が少なくないこと、一方で、長年蓄積してきたデータがあるが故に、現在では不経済な方法でも継続するのが得策な分野があることもわかった。
Wikipediaでも自分で調べることはできなくはないが、本の形で整理されていると、適切な機器を用いればGNSSの利用で極めて高い精度で高度を含む位置を知れること、SARやInSARがどんな原理で、どう応用されているかも体系的に学習でき有用である。
地震の研究に関われば、結局は地球のモデル化を進めていくしかないことがわかってくる。地震が起きている近傍だけで見ても見えてこないことが全球の視点で仮説化されたモデルで説明できることがある。今のモデルでは地震や火山噴火を予知することは難しいが、起きた事象を説明できるようにはなって来ているのもわかる。潮汐力の話も、固体潮汐、海洋潮汐などモデルの構成要素の詳細化が進んでいることがわかる。単純には月の動きと潮の満ち引きが連動することは覚えていたが、太陽との位置関係で大潮が決まるのは忘れていた。さらに、地面だってカチカチではなく、地面も上下する固体潮汐が毎日数cm起きているのには驚かされた。大地震で位置は数m単位で動くが、そうでなくても日々プレートの活動の影響をうけて動いている。全球で見ている視点では、三角点も移動地物となる。地面は動かないと思わないと日常生活には不都合で、その時その時でGoogle Mapの地物の座標が変わってしまったらたまったものではない。それでも位置計測の精度が上がってくれば、その差の大きさが無視できなくなるだろう。どの時刻での計測値かを記すのが当たり前になる時代もやがて来るだろう。
読み終わって反芻すると、副題の『宇宙から見る「水の惑星」のすがた』の水の位置づけの大きさが染み入ってくる。本書を読むことで水の重量が様々な影響を与えていることが理解できるし、固体の水(氷)が液体の水に変わることの影響の大きさもある程度想像できるようになる。
本書では、オープンデータ化の傾向が書かれていて楽観的なトーンが感じられるが、トランプの出現などの問題から世界の分断が進んでしまうと研究の進歩が遅れてしまうことが懸念される。